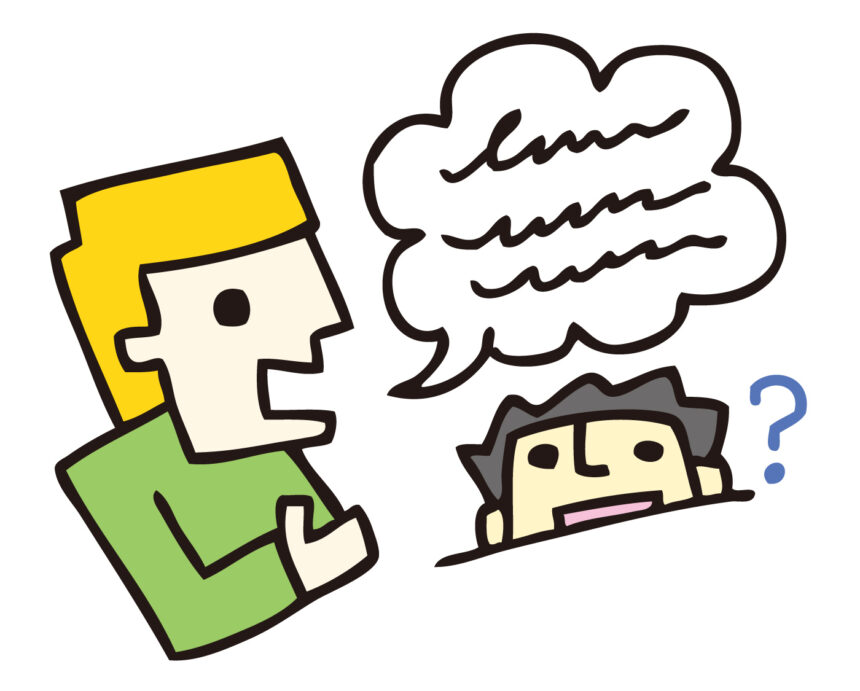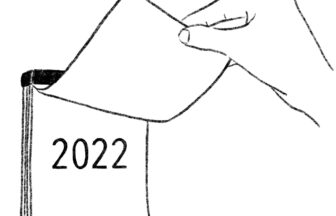「私、全然書けないんですよね…」
文章添削士養成講座では受講生の方に文章を書いてもらう課題があります。課題を出してもらった上で講義の中で「ここは良いですね」とか「ここを改善するとさらに良い文章になります」といった形で講師から解説を受けるという流れで進んでいくのですが、実際に養成講座のアシスタントを務めていると受講生の方から「書けない」という感想をもらいます。
私がその受講生さんから提出されてきた課題の答案を読んでいると、ある程度のレベルに達しているにも関わらず、なぜそのような感想が出るのかなぁ…と思っていました。
しかし、あれこれ考えていくうちに、
自分の伝えたいことが文章に表現できない
というもどかしさを持っている方が多いことに気付きました。
自分が伝えたいことを確実に伝えるためには、文章の型を覚えて実際に書くだけでなく、自分が使うことができる「語彙」を増やすことが必要です。いくら文章を書くことが得意でも、自分が伝えたいことを確実に伝えるだけの「語彙」を持っていないと自分と同じ思考力を持っていない限り他人には伝わりません。
では「語彙」を増やすために最も効率の良い方法は何でしょうか?
それは「読書」をすることです。
読書をすることであらゆるジャンルの作家さんが書く文章から語彙も一緒に学ぶことができます。
しかし「忙しくて時間が取れない」「読む習慣がないので続かない」と思われている方も多いのではないでしょうか。
そんなあなたにお薦めなのが文章添削士協会考案のメルマガ教材「ポルタ(porta)」です。
文章作成のプロである文章添削士が厳選した文章が揃っています。また、大学受験を意識した論理的な文章が読めるので、自分で本選びをする必要がありません!
そして、長文が苦手な方でも問題ありません。丸ごと1冊ではなく、本の核となる一節を厳選しているため、通学途中などの隙間時間に読むことができます。年間52本の書籍と出会えます。
まずは無料サンプルを購読してみてください!
↓こちらからどうぞ↓
小論文メルマガ教材「ポルタ」|(一社)文章添削士協会 (tensakushi.or.jp)
(茅根 康義)